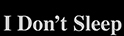8/ 13th, 2010 | Author: Ken |
一枚の写真
1枚の写真がある。一人の裸足の少年が幼児を負い直立不動で立つ、ただそれだけのモノクローム写真である。初めて見た時、背筋に戦慄が走った。
慄然とし、そして涙を禁じ得なかった。写真が持つ力とは何なんだろう? どうしてこんなに心に迫ってくるのだろう?
…..僕は時空を越えてカメラマンの立つ場所に立ち、彼の視点で見ている。そして自分を少年に同化させ、また死んだ幼児にも自分を重ね合わせてしまう。少年の負った過酷なドラマも想像してしまうのだ。彼の両親は原爆で亡くなったのだろうか、背の児はたぶん弟なのだろう…。時代の風潮として軍国少年で育った彼は、男なら決して涙を流してはならないし、大和男の子として身じろぎもしない姿勢こそが少国民の誇りと教えられたのであろう。
…僕は戦争の記憶は全くないが背の幼児が生きてていればおそらく同い年のはずだ…。
撮影者ジョー・オダネル氏は…。長崎で死体を燃える穴の中に次々と入れている焼き場に10歳ぐらいの少年が歩いてくるのが目に留まった。おんぶ紐を襷にかけて、幼子を背中に背負っていた。少年は焼き場のふちまで来ると、硬い表情で目を凝らして立ち尽くしていた。
「少年は焼き場のふちに、5分か10分も立っていたでしょうか。白いマスクの男達がおもむろに近づき、ゆっくりとおんぶ紐を解き始めました。この時私は、背中の幼子が既に死んでいる事に初めて気付いたのです。男達は幼子の手と足を持つとゆっくりと葬るように、焼き場の熱い灰の上に横たえました。まず幼い肉体が火に溶けるジューという音がしました。それからまばゆい程の炎がさっと舞い立ちました。真っ赤な夕日のような炎は、直立不動の少年のまだあどけない頬を赤く照らしました。
その時です、炎を食い入るように見つめる少年の唇に血がにじんでいるのに気が付いたのは。少年があまりきつく噛み締めている為、唇の血は流れる事もなく、ただ少年の下唇に赤くにじんでいました。夕日のような炎が静まると、少年はくるりときびすを返し、沈黙のまま焼き場を去っていきました」。「写真が語る20世紀 目撃者」(1999年・朝日新聞社)より
Joe O’donnell (ジョー・オダネル): 1923年、アメリカ・ペンシルベニア州に生まれ、海兵隊に入隊、米軍調査団カメラマンとして被爆直後の長崎を撮影。戦後ホワイトハウス付カメラマンとして、歴代の大統領の写真を撮影。 上記写真のネガは長らく自宅の鞄にしまい込まれていたが89年に米国内の反核運動に触発され鞄を開け、90年米国で原爆写真展を開催。日本では写真集「トランクの中の日本」(小学館 )。 2003年に長崎を再訪問し、撮影した当時の少年・少女と再会。07年8月9日没。