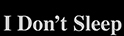2/ 4th, 2010 | Author: Ken |
審判
「The Trial・審判」1963 原作:フランツ・カフカ 監督:オーソン・ウェルズ 出演:アンソーニー・パーキンス、ジャンヌ・モロー、ロミー・シュナイダー、エルザ・マルチネリ。奇才、異才、鬼才、怪優、怪演、オーソン・ウェルズがカフカの世界にトライした。画期的な「市民ケーン」以来、「偉大なるアンバソン家の人々」「上海から来た女」など細部には眼を見張るところがあるが映画としては失敗作だ。しかし「審判」は彼の才能が遺憾なく発揮されている。カフカ的悪夢の世界だが、オープニングは「城」から始まる。法という城門に男が入ろうとする。彼は入ろうとするのだが堂々巡りするだけだ。そこには誰も来なかった。そこは彼のための法の城門だったからである…。ジョゼフ・Kは普通の男である。ある朝検察官が刑事とともにやって来た。Kは罪に問われたと言う。何の罪かは検察官にも解らない。法廷、インチキ裁判、叔父、弁護士、女、裁判所所属の画家。誰もKを救う事ができない。夜明けにKは逮捕され、荒野のような空き地で犬のように殺された。
不条理、ナンセンス、蛇が自分の尻尾を飲み込むウロボロスのような終わりのない苛立ち。Kは何故、不条理にも殺されなければならないのか。…. 近づく全体主義の不安か?ナチスの軍靴の音か? 官僚機構のがんじがらめの社会か?
映画はモノクロームのコントラストを強調して美しい。廃駅ガール・ドルセー(現オルセー美術館を使ったセットなど驚くほどの凝り方だ)。音楽は自らを音楽貴族と呼んだディレッタント、トマゾ・アルビノーニのソナタ(アダージョ)が効果をあげている。
しかし、バロック音楽というと必ず取り上げられる名曲だが、アルビノーニの作ではない。レモ・ジャゼットという音楽研究家が、ザクセン国立図書館から受け取ったアルビノーニの自筆譜の断片をもとに編曲したというが、アルビノーニの証拠はどこにもなく、「ト短調のアダージョ」は完全なジャゾットの作である。でも、99%の人がアルビノーニと信じている。(僕もそうだった)
(松田優作の「野獣死すべし」にも使われていたがひどいものだった。アルビノーニに失礼だろう)。
このカフカの不可思議な小説を巡って様々な論があるであろう。しかし、この映画はオーソン・ウェルズの「審判」だ。理解しようとするほど理解できない仕組みである。彼の最終作「フェイク」は現実かマジックかが混在し解らないのがフェイクという、人を食ったやり方。そこがウェルズだ。彼の哄笑が聞こえてくるようだ。