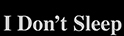12/ 6th, 2011 | Author: Ken |
嵐を呼ぶ男たち … Drum Battle
古い話だが裕次郎の大ファンの友達にいて「嵐を呼ぶ男」を見に行こうと誘われた。田舎町の映画館に中学生が二人して出かけた訳だ。ぼくはひねくれ者だから友達のようにとてもスゲエ!なんて思えないし、ドラム合戦の最中に痛めた手がスティックを落とす。と、マイクを引き寄せ歌い始めるんだ。〜オイラはドラマー〜ヤクザなドラマー〜そうしたら観客が熱狂して、白木マリだったかしらリズムに乗せて踊り始めるのだ。バンドも調子に乗って盛り立てる….。と、こういう訳だ。ぼくはそのころスィングなんて言葉もジャズもブルースの真の意味も知らなかったけれど(まあ、〜何とかブルースという歌謡曲なら知っていたけどね)。子どもながら正直照れましたね。おいおいそれジャズじゃねーだろ。だって歌に全然ビートないし、いくら芝居だといってもあの歌で興奮するわけ無いじゃん。あの当時は時代背景としてジャズが流行っていたんですね。ロカビリーなんてのも大流行りだった。進駐軍とそのキャンプで日本人もジャズを演奏したり憶えたりしたりで、後に彼らがビッグネームに育ったのだ。
高校生になりジャズの洗礼を受け本格的に聞き始めた。アート・ブレイキー、ホレス・シルバー、MJQなどのコンサートに無理して通った訳よ。輸入LPなんて手が出ないからジャズ喫茶(ミナミのバンビが多かった)に入り浸りになったりしてね。そこでブルースとは何ぞやとかインプロバイゼーションとか、ソゥルとかハードバップなんて言葉も憶えていった。
確か1964年だったと思う。4大ドラマーの血戦「ドラムバトル」がやって来たのだ。マックス・ローチ、ロイ・ヘインズ、フィリー・ジョー・ジョーンズ、シェリー・マン。そしてチャリー・マリアーノ、秋吉敏子、リロイ・ヴィネガートという錚々たる顔ぶれだ。端正で毅然としたローチ、奔放なフィリー・ジョー、危なげないヘインズ、そしてマンのクールなブラシワーク…。2回目のドラムバトルはアート・ブレイキー、トニー・ウイリアムス、エルビン・ジョーンズ、ケニー・クラーク?(ここの記憶が曖昧なのだ、確かケニー・クラークだったと思うのだがプログラムを無くしてしまった。誰か教えてください)。まあ、音楽の歓び、感性、興奮なんて到底言葉では表現できないものだから、当時無理して買った彼らのLPレコードをご紹介しよう。
●ローチとソニー・ロリンズには名盤が多過ぎるのだが「Worktime」、この「It’s All Right With Me」なんて!豪放で超スピードのフォーバースの掛け合い。これを聞くだけで嬉しくなってしまう。そしてクリフォード・ブラウンとのセッション。ブラウニーが本当によく歌い〜ああ、なんて素敵なんだ!….ドラムは本来リズム隊なのであんまり出しゃばると面白くない。長いドラムソロは聴き辛いね。
●フィリー・ジョーはサイドメンとして数々の名盤に登場している。マイルスとの一連のレコード、どれもこれも最高の出来だ。そして有名すぎるソニー・クラーク、J・マクリーンとの「Cool Struttin’ 」”気取り歩き”というその名の通りジャケットも新鮮であった。
●シェリー・マンはウェストコーストの白人でありハードバップの泥臭さや暑苦しさは少ないけれど、その軽い乗りが素晴らしいんだ。「Manne Hole」の「朝日のごとく爽やかに」なんてコンテ・カンドリーのトランペットが歌いリッチー・カミューカのテナー、一杯飲りながらいつまでも聞いていたくなりますね。
●ロイ・ヘインズは何でもこなす名手なんだが、ローランド・カークとのレコードなんて!カークのアーシーで、アブストラクトで激しい演奏は迫力満点だ。このフルートを聞いてみてよ!そして「We Three」このトリオ演奏は歌うようなドラミング、多彩なテクニック。息の合った三人の緊張感が心地いい。
もうジャズを聴かなくなって30年も経つ。何故かッて?ジャズとは演奏者にこそ意味がありその個性と技能、表現なんだ。そしてその時代を切り開く全く新しいサウンドにこそ意味があるのだ。彼らが歳を取り情熱が薄れ自己模倣の繰り返しになれば、それはもうモダンジャズじゃない。懐メロだ。名手たちが去り次代の若者たちも革新を失った。それはジャズというスタイルの音楽であり軽音楽の一派でしかない。もっと過激であれ!いままで聴いたことのないサウンドを聴かせてくれ!あの時代にはあんなに熱く激しくあったじゃないか!